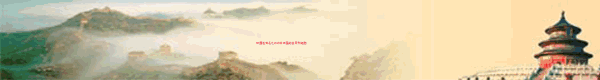
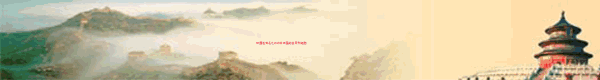 |
|
| 張春侠=文・写真 |
人民中国雑誌社はこの秋、于明新社長を団長とする八人の代表団を日本に派遣し、各地で『人民中国』の読者の皆さんと交流会を開きました。いまや中国が発行する唯一の日本語による雑誌となった『人民中国』に対し、読者から多くの温かい励ましや厳しい注文をいただきました。と同時に、どこでも情熱溢れる歓迎を受け、より良い雑誌づくりのためいっそう努力しなければならないと、決意を新たにする旅でもありました。 団員の一人で、編集部に所属する張春侠記者が、埼玉県飯能市で開かれた『人民中国』の読者会との交流の感想をまとめました。(編集部) 熱心な読者に感激する
今回私は、生まれて初めて日本の土を踏んだ。日本へ行く前、『人民中国』の読者は非常に熱心だと聞かされていたが、日本で多くの『人民中国』の読者と交流し、それが本当だったことを実感した。 東京から電車で埼玉県飯能市に行ったのは9月8日のことだった。飯能駅の改札口を出ると、飯能市の三誌(『人民中国』『北京週報』『中国画報』)読者会の大野邦弘会長と広瀬拝子事務局長が出迎えに来てくれた。 お二人の案内で、古稀閣という中華料理店に向かった。店に入ると、大きな拍手がわきおこった。早くから待っていた十数名の『人民中国』の読者の皆さんが次々に立ちあがり、私たちを歓迎してくれた。 ほとんどの人が初対面だったので、まず簡単な自己紹介をしようということになった。車椅子を乗ってやってきた元の会長の西野長治さんは、八十七歳の高齢だった。西野さんは「訪日団の中に若い人が多いのを見て、たいへん嬉しく思う」といい、「日中両国の架け橋として、『人民中国』が両国友好のため引き続き役割を発揮してほしい」と私たちを励ましてくれた。
東京からわざわざやって来た特別会員の小林泰さんは、団の中に『人民中国』の李富根副社長を見つけると、「去年、『人民中国』創刊50周年の時、北京で会いましたが、覚えていますか」と手を差し出した。李副社長も「覚えていますよ」と答え、二人は手を握り合った。 私は日本に知人はいないので、読者は私のことなぞ知らないと思っていた。ところが于社長が私を紹介すると「あなたが張春侠さんなの。若いね!」とみなが親しげに言った。「『人民中国』であなたの書いた文章をたくさん読みましたよ」というのだ。私は驚き、そして胸に熱いものがこみあげてきた。読者とわたしの距離は急に縮まったように感じた。 こうした歓迎セレモニーの模様を、一人の若者がビデオカメラで撮影していた。そして、飯能ケーブルテレビの和泉由起夫社長と一緒に、そそくさと会場を出て行った。「読者会が資料ビデオでも作っているのだろう」と私は思っていた。
だが、宴会が始まり、暫くすると、和泉社長が戻ってきて座席についた。そしてこう発表した。 「訪日団と読者の交流の模様は、ケーブルテレビを通じ、埼玉県の飯能、入間、所沢などの六市に放送されました。埼玉新聞社も今度の活動を報道するでしょう」 「彼らが宴会場を出て行ったのはそのためだったのか」と私はやっと悟った。と同時に、彼らの仕事に対する真剣な取り組みに心から感心した。 私たちは心おきなく語り合った。三誌担当の萩原勝吉さんは、以前から中国に大変興味を持っていて、飯能の読者会が成立する前から『人民中国』を読んでいたという。1986年に初めて中国を訪れ、中華料理が大好きになった。その後、彼は本場の中華料理の味が忘れられず、毎年一回は、中国に出かけた。「中華料理は美味しすぎる。中国に行くたびに美味しいものを食べすぎ、肥ってしまい、膝を悪くした。だから腹が引っ込んだらまた中国に行くことにしています」と荻原さんはユーモアを交えて言うのだった。
読者の皆さんと私たちがもっとも熱心に話し合ったのは、『人民中国』の内容やその編集、レイアウトなどについてだった。木村良次さんはこの日、一冊の『人民中国』をわざわざ持ってきていた。その本の中には、さまざまな記号がいっぱい書き込まれていた。『人民中国』が届くたびに木村さんは、全部に目を通し、気に入った記事に印をつけるのだという。 「この数年、『人民中国』は大きく変わった。文章も写真もレイアウトも良くなった」と多くの読者からお褒めの言葉をいただいた。連載中の「世界遺産」や「中国語新辞苑」はなかなか評判がよかった。 広瀬事務局長は「わたしの一日」について「企画は新鮮だが、狙いがよくわからない」と疑問を呈した。他の日本の雑誌に比べ、文字が多すぎる、広告の位置が雑誌の前の方に来すぎているのではないか、という問題提起もあった。 いずれも『人民中国』をもっと良くするための貴重な意見だった。私たちはこうした意見を真摯に受け止め、今後の雑誌づくりに生かしていきたいと思う。 竹の寺で感じた日本の風情
その日、私たちは、大野会長が住職をしている竹寺に招かれた。飯能市から車で山道を約30分、青々と茂った山道を登って行くと竹寺がある。静けさと幽玄の中に、鳥のさえずりが時々聞こえてくる。 「竹寺は、日本で数少ない神仏習合の寺です。竹が多いことで世に知られ、一年中、多くの善男善女がお参りに来ます」と大野会長は説明した。 竹寺には牛頭天王が祭られている。牛頭天王は、インドの祇園精舎の守護神といわれ、中国に伝わってから密教、道教、陰陽思想と習合した。さらに日本に伝わり、陰陽道とのかかわりを深めた。 1992年、中国人の有志からブロンズ製の「牛頭明王」像が寄贈された。台座の銘は、前中国仏教協会会長の趙朴初が書いている。 中国からの訪日団を歓迎するため、夕暮れの淡い光の中で、和服を着た日本の夫婦が琴を演奏してくれた。大野会長の友人の医者、高橋通夫さんとプロの演奏家の高橋澄子さんである。夜のとばりが静かに降りて行くなかで、竹寺に流れる琴の音が、風に揺れる竹の葉の擦れ合う音と溶け合い、俗世間を超越した境地にひたった。 夜になって、食事の時間が来た。竹寺では美味しい精進料理があると聞いていたが、食堂に入ると素晴らしい光景が目に飛び込んできた。真っ白なテーブル掛けに並んださまざまな食器は全部、竹製だった。盃、皿、茶碗、箸は言うまでもなく、清酒を入れる酒器まで竹で作られていた。「すばらしい、これは工芸品だ」という驚きの声があがった。 また、料理のまわりには、さまざまな草花が飾り付けられていた。さらに、それぞれの料理には、料理にあった漢詩を書いた紙が添えられていた。いにしえの中国の文人たちが詩を吟じながら、茶を味わい、酒を飲んだ様子を彷彿とさせるものだった。 読者会の会計担当の沼井成さんが、もうすぐ離任しようとする人民中国雑誌社東京支局の前支局長、張哲を歓送するため、浴衣を贈ってくれた。張哲は感激し、その場で、もらった浴衣に着替えた。雰囲気はすっかり打ち解けた。 充実した誌面を目指して
飯能市の三誌読者会が誕生したのは1990年である。それ以来、毎年、少なくとも三回のイベントを行うことになっている。東京駐在の中国の記者たちに来てもらい、講座や春節(旧正月)祝賀会などを通じ、中国に対する理解を深める活動をしてきた。 さらに毎年一回、会報を出し、たびたび読者の中国訪問旅行を組織した。現在、読者会の会員は49人になり、毎回、2、30人がイベントに参加している。 しかし『人民中国』の将来に問題はないのか。大野会長は「私もいくらか心配している問題があります」と切り出した。それは他のメディア、とくにインターネットの影響であるという。「以前は、『人民中国』が日本で中国を知るための唯一の窓口であり、戦争を経験した人や中国に関心のある人が、中国に対する理解をいっそう深めるために読者会に入りました。しかし今は、メディアが多元化し、『人民中国』も日本のほかの月刊雑誌と同じように、インターネットからの圧力を受けているのです」というのである。 こうした状況に対応して飯能の読者会は、中国にとくにかかわりがある人ばかりでなく、中国に少しでも関心を寄せている人に『人民中国』を読んでもらう活動を続けている。とくに、2008年に開催される北京オリンピックに日本の人々が関心を持っているので、これからはオリンピック関連の話題をより多く掲載した方がよい、という提案もあった。 翌日、飯能市を去るとき、飯能駅には大野会長と広瀬事務局長が見送りにきてくれた。中国語を勉強している広瀬事務局長は「私はもう年ですから。髪も白くなってしまいました」と中国語で言った。私も日本語を勉強したいと思っているというと、「それならこれから、お互いに先生になりましょう」といい、電子メールのアドレスを教えあった。 東京に戻る電車の中で、わたしは胸が一杯になった。飯能の読者会のような熱心な読者が、日本の各地にたくさんいるのだ。その読者のために、私たちは中国の真の姿を紹介する、中身の濃い原稿を書いて行かなければならない。そう思うと、身が引き締まる思いがした。 |