建築史が映し出す社会発展史
劉檸=文
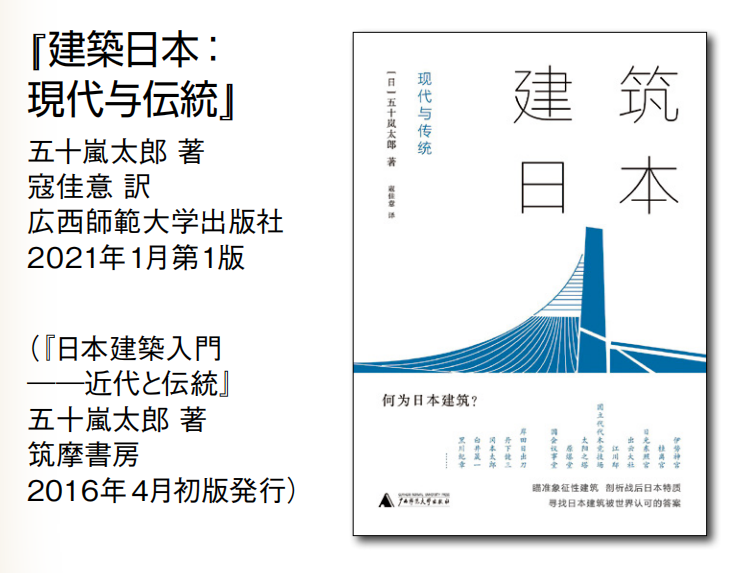
建築史は、社会史・文化史、そして対外文化交流史をも映し出している。
西洋の建築様式が日本に上陸してから、「日本とは何か」という自己認識問題は、ずっと日本の建築家の頭から離れることがなかった。伝統的なものの価値において、多くの著名建築家、たとえば菊竹清訓・黒川紀章などはみな、形のある様式や装飾に比べると、その思想・美意識などの方面における精神性をより強調している。例えば黒川は、「二次元性」は日本文化の中に普遍的に存在するものと考え、論文「グレーの文化」の中で、「絵画絵巻のように多点透視図法を使うこともできる」と指摘しており、都市空間を「平面的要素に分解」している。
今日、こうした「二次元」風の都市計画と建設設計理念は、確かにすでに日本中に広がっている。東京の六本木や日本橋などの、新たに開発された高層オフィスビルや総合商業施設が建ち並ぶ街を歩くと、ビルの谷間にはびっしりと路地が張り巡らされ、道端にはビルの低層階のテナントや独立した店舗があって、建築空間の内と外との境界はあいまいで、外がまるで内部の延長のようで、コンクリート・ジャングルの中を歩くような抑圧感や退屈さを全く感じることはなく、「散歩指数」が大幅にアップしている。建築史と都市計画史の中で代表的な例が、代官山の複合施設「ヒルサイドテラス」だ。これは建築家の槇文彦が、ここの地形の高低差を利用しながら、日本の伝統建築の中の「間」や「奥」などの概念を極致まで発揮させてつくり上げた街角風景の極致である。
私は東京の街角を散歩し、近年新たに完成したスマート型複合商業施設を間近に観察することがとても好きだ。それらのビルは巨大で、構造が超複雑ではあっても、機能性と美学が見事に統一され、精緻極まりない機械であるかのように、余分なものは一切ない。単体の建築だけでなく、1棟あるいは数棟の総合施設を中心とする地区は、とても美しい「都市の中の都市」をも造り上げている。内部は機能別に区分けされ、粗と密が趣きに富み、一周また一周と外に向かって広がり、内部の連絡通路は車が行き交う外部の道へとつながり、そして直接鉄道駅につながっている。中心商業施設から地区全体、そして街全体が一つの有機体のようであり、衆に抜きん出るだけでなく、心が癒やされる独立したブランドのようだと感じるかもしれない。一つ一つの独立ブランドとしてのエリアが、人を幻惑する大都会東京を形づくっているのだ。
いかなる意味からも、これは視覚景観上においてほとんど隙がなく、かつ高度に自己完結したシステムである。しかし包み隠さず言うならば、高度に合理化されたシステムもまた一つの問題をはらんでいて、それはシステムの閉鎖性だ。建築史家である東京大学の鈴木博之教授は、「新国立競技場問題でザハ・ハディド案を排除したのに現れているように、日本(の建築界)は今、閉ざされた道を選んで歩んでいます」と鋭く指摘した。
鈴木が言及した問題はかなり本質的なもので、この指摘は建築史のものというより、文化史のものだと言ったほうがいいかもしれない。理論上では高度に自己完結したシステムにとって、閉鎖性は必然的に付随するものだ。システムが無限に自己進化を遂げるのでなければ、遅かれ早かれ外部の圧力に直面せねばならず、それが時勢に順応し、外部エネルギーを吸収し、存在の危機を内部変化のチャンスに変えることができれば、新たなバランスを取り戻すことができる。